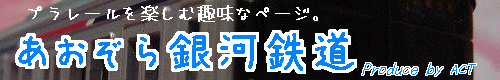 あおぞら銀河鉄道―プラレールの架空鉄道― | ||
| ■機関車 ○EF15形電気機関車 ○EF60形電気機関車 ○EF63形電気機関車 ○EF65形電気機関車 ○EF66形電気機関車 ○EF81形電気機関車 ○EF200形電気機関車 ○EF210形電気機関車 ○EH200形電気機関車 ○EH500形電気機関車 ○EF510形電気機関車 ⇒8620形蒸気機関車 ○C11形蒸気機関車 ○C12形蒸気機関車 ○C53形蒸気機関車 ○C56形蒸気機関車 ○C57形蒸気機関車 ○C61形蒸気機関車 ○C62形蒸気機関車 ○D51形蒸気機関車 ○7100形蒸気機関車『義経』 ○DD51形ディーゼル機関車 ○DF200形ディーゼル機関車 ○HD300形ハイブリッド機関車 |  ▲8620形蒸気機関車(58654号機)SL人吉 日本国有鉄道の旅客用テンダー式蒸気機関車。 大正時代の標準型として1914年から1929年の間に672両が製造された機関車。他にも樺太庁鉄道8620形(15両)、台湾総督府鉄道500形(43両)、北海道拓殖鉄道8620形(2両)という同型機関車がある。 最初は東海道本線や山陽本線などの幹線向けに使用されていたが、より高性能な機関車が投入されてくると置き換えられ、次第にローカル線へと活躍の場を移していった。この機関車は平坦で距離の長い路線に向いており、客貨両用に効率よく使えるという特徴を持っていたことから長く愛用されており「鉄路あるところ、ハチロクの機影見ざるはなし」とも形容されるほどの名機であった。その後、樺太庁鉄道が鉄道省に移管された後、14両が樺太へと送られた。戦後はソ連に接収されており、その後の動向は分かっていない。その他の同型機は戦後の復興にも大きく貢献し、蒸気機関車の時代が終焉を迎える1970年代まで多くの機関車が活躍していた。 製品になっている58654号機は、JR九州において動態保存され活躍している。以前は人吉鉄道記念館に保存されていたが、1987年12月に小倉工場へ運ばれて動態復活に向けた整備が始まった。ボイラーが新日本製鐵の手によって新製されるなど、動態復活には並々ならぬ、発足当初のJR九州の本気を感じるものがある。1988年8月28日より豊肥本線『SLあそBOY』、肥薩線の『SL人吉号』として運転が開始されていた。その後は修理を受けつつも活躍を続けていたのであったが、台枠の歪みによる車軸への負担がかかり、車軸焼けを起こすなど、修復不可能と判断された。列車は運転を休止、機関車は一旦静態保存へと移行することとなってしまった。 その後、日立製作所に新製当時の図面が残っていたことに加え、九州新幹線開業による観光資源として活用できるという判断がなされ、2007年2月21日より大規模修繕が行われ、2009年4月25日より、熊本〜人吉間でSL人吉として復活。運転が開始された。この際、台枠を日本車輌で新製、ボイラーをサッパボイラで修復、客車の修復などに巨額が投じされている。それだけJR九州がこの機関車にかけた期待の大きさが現れているのかもしれない。  ▲58654号機(SL人吉)  ▲SL人吉客車 動力の小型化などにより、機関車の前輪辺りが電池をセットする場所となり、動力は運転室部分に設置されている。出来るだけ目立たないように苦心されている部分が見え隠れするが、走行具合は決して悪くはない。牽引される客車(50系)はプラキッズを乗せられる仕様となっている。  ▲58673号機 上記の50系客車をもう1両確保するため、もう1セットを購入。このままでは番号被りが生じるため、TEPRAで『58673』のラベルを作成。ナンバープレートを模したシールの上から貼った。その後、PCゲーム『まいてつ』(Lose公式ホームページ)に出てくる、8620形蒸気機関車に取り付けられているタイプと同じヘッドマークを貼り付け。 | |
Copyright(C)2006-2016 AozoraGingaRailway.All Rights Reserved. | ||